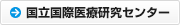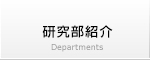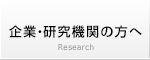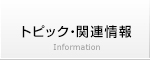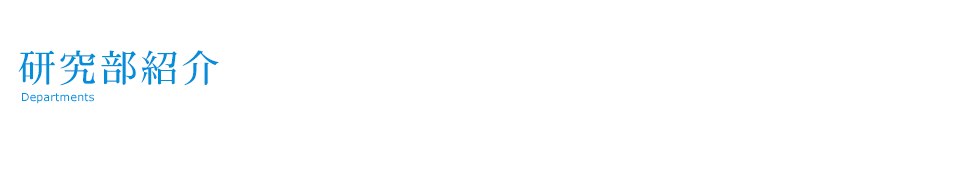造血システム研究部
研究紹介
ヒトの体内には多種多様な細胞が存在しますが、その過半数を占めるのが血液細胞です。血液細胞は、酸素の運搬、免疫機能、止血といった重要な役割を担い、個体の恒常性を維持するうえで不可欠な存在です。これらの血液細胞は、出生後の哺乳類において、骨髄内に存在する造血幹細胞によって産生されます。造血幹細胞は、最も未分化な血液細胞であり、自己複製能と多分化能を有する細胞として知られています。
当研究部では、造血幹細胞とそれに由来する血液細胞、およびそれらの産生に関わる多様な細胞や臓器を含めた「造血システム」を研究対象としています。特に、造血システムがどのように確立され、機能し、個々の細胞がどのように寿命を迎えるのか、さらにはこれらがさまざまな病態においてどのように変化するのかを解明することを目指しています。
造血幹細胞は、骨髄内の「ニッチ」と呼ばれる微小環境の影響を受けながら、静止期の維持、増殖、未分化状態の維持や分化といった細胞運命を決定します。ニッチと造血幹細胞の関係性は、ストレスや加齢の影響を受けることが知られており、その結果、各種の血液疾患や血液以外の疾患の発症にも関与すると考えられています。したがって、造血幹細胞とニッチを起点とする造血システムを包括的に理解することで、こうした疾患の成因や個体老化の背景にあるメカニズムを解明できると期待されます。さらに、造血幹細胞は、白血病をはじめとする造血器腫瘍の根治療法として行われる造血幹細胞移植にも用いられています。そのため、造血幹細胞の時空間的な動態を自在に制御する技術を確立することで、移植医療の発展にも貢献できると考えています。
こうした研究課題に取り組むため、当研究部では、単一細胞解析技術、造血幹細胞の培養法・遺伝子編集技術、リアルタイム代謝解析、in vivoイメージング、全骨髄イメージング、AIなど、最先端の解析手法を駆使し、造血幹細胞とニッチの相互作用やその制御機構の解明を進めています。これらの研究を通じて、生理的および病的な造血システムにおける分子機構を明らかにし、再生医療につながる幹細胞の維持・増幅・移植技術の開発、さまざまな病態や加齢変化の理解、さらには新たな疾患治療法の開発を目指しています。
主要スタッフ
| 部長 | 田久保 圭誉 |
|---|---|
| 研究員 | 森川 隆之 藤田 進也 綿貫 慎太郎 反町 優理子 |
| Student Researcher | 須藤 光(東京科学大学) |
| 研究生 | 樽井 謙英(早稲田大学) |
| ラボマネージャー | 原口 美帆 玉置 親平 |
| 客員研究員 | 小林 央(東北大学) 雁金 大樹(東京科学大学) 笠原 秀範(大阪大学) 城下 郊平(San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy) 加部 泰明(高知大学) |
★オープンな研究環境で最先端の幹細胞研究に携わってキャリアを一歩先に進めてみませんか?私たちの研究室は学位研究や卒業研究を希望する方を受け入れています(過去実績:慶應義塾大学、早稲田大学、横浜市立大学、東京理科大学、東京科学大学、東北大学)。
研究所には博士課程の大学院生を経済的に支援するStudent Researcher制度もあり、当研究室からの希望者はこれまで全員が採用されています。
田久保の併任先の東北大学大学院医学系研究科に所属しての学位取得も可能です。
また、学振特別研究員への採用を目指した指導にも力を入れており、これまでにのべ8名の方が採用されています。
興味のある方や見学希望の方は田久保(takubo.k[at]jihs.go.jp *[at] はアットマークに置き換えてください)までお気軽にご連絡ください。