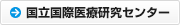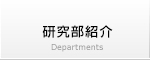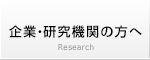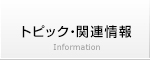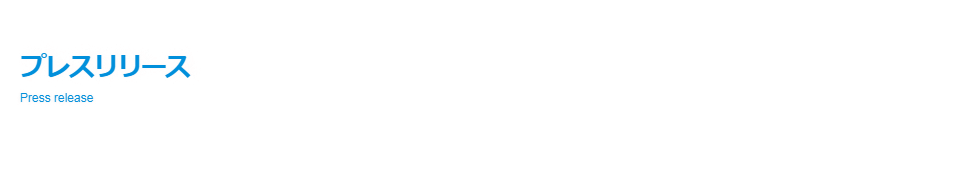ホーム > トピック・関連情報 > プレスリリース > 加齢による造血幹細胞生着不全の機序を解明 骨髄代謝・血流動態の変容が起因
加齢による造血幹細胞生着不全の機序を解明
骨髄代謝・血流動態の変容が起因
2025年7月4日
東北大学
国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
発表者
田久保 圭誉(国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所 造血システム研究部長)
発表のポイント
- 白血病などの造血器疾患の根治を可能とする造血幹細胞 (HSC) 移植の成功率が加齢と共に減少する原因の一端を明らかにしました。
- 骨髄では血球細胞により産生されるアセチルコリンを起点とした一酸化窒素 (NO) シグナル経路(注1)によって血流が保たれており、加齢によりその機能低下が見られることが判明しました。
- 骨髄では血流による類洞血管内皮細胞 (注2) の活性化により、移植した造血幹細胞 (HSC) (注3) の骨髄への生着効率 (注4) が維持されていました。
- 高齢個体で低下したHSCの生着効率は、加齢により減弱するNOシグナル経路の再活性化や、骨髄類洞血管の活性化により改善が見込まれる可能性が示されました。
概要
これまでHSC移植時のHSCの生着率は加齢に伴い低下することが知られていましたが、その要因は明らかではありませんでした。
東北大学大学院医学系研究科幹細胞医学分野および国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所 造血システム研究部の田久保 圭誉教授・部長、同部の森川 隆之上級研究員ら、神奈川県立産業技術総合研究所の研究グループは、この要因として骨髄の局所血流・代謝に着目し、加齢による血流の減少に加え、血管拡張を担うアセチルコリンや一酸化窒素 (NO) を介するシグナル経路の減弱を認めました。このとき血液と血管壁の間に血流によって生じる力であるずり応力(注5)も、骨髄類洞血管で加齢により低下することがわかりました。HSCの骨髄への生着におけるずり応力の役割を検証したところ、移植後HSCの生着効率の加齢による低下は、アセチルコリン-NOシグナル経路の加齢変化が一因であることが示されました。同シグナル経路が高齢個体での移植効率の改善に向けた有効な治療標的となりうることが期待されます。
本成果は、2025年7月1日付で学術誌Nature Communicationsに掲載されました。
用語説明
(注1)一酸化窒素 (NO) シグナル経路:
動脈系においてはアセチルコリンなどによって血管内皮細胞のNO合成酵素が活性化しNO産生が上昇します。NOが内皮細胞に近接した血管平滑筋細胞を弛緩させることで血管が拡張します。
(注2)類洞血管 :
骨髄の血管の中で上流側の動脈などと比較して径が太く、下流側にあたる血管です。主にこの類洞血管の壁を介して血球細胞や物質が血管内外の行き来をしているとされます。
(注3)造血幹細胞 :
分裂することで生涯にわたってあらゆる血液細胞を供給している細胞です。哺乳動物の成体では主に骨髄に存在している数少ない細胞です。
(注4)生着 :
造血幹細胞移植において、移植した造血幹細胞が血中から骨髄に移行したのち、造血を開始することを生着と言っています。
詳細は以下のファイルをご覧ください。
♢リリース文書