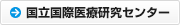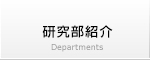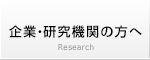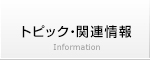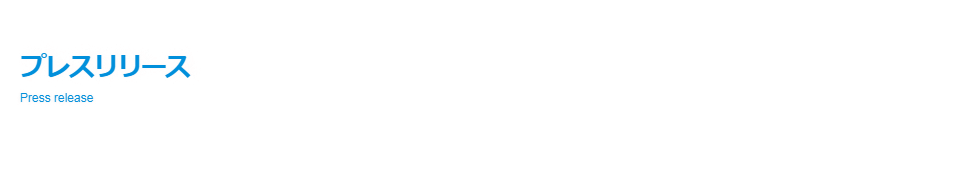ホーム > トピック・関連情報 > プレスリリース > ゲノム解析で明かされた人類の移動と進化-北アジアから南アメリカまでの約2万キロにおよぶ移動経路を解明-
ゲノム解析で明かされた人類の移動と進化 -北アジアから南アメリカまでの約2万キロにおよぶ移動経路を解明-
金沢大学
国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所
総合研究大学院大学
発表者
徳永 勝士(国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所 ゲノム医科学プロジェクト長)
概要
金沢大学医薬保健研究域医学系/医薬保健研究域附属サピエンス進化医学研究センターの田嶋敦教授、国立国際医療研究センター(現在:国立健康危機管理研究機構)の徳永勝士ゲノム医科学プロジェクト長、総合研究大学院大学 統合進化科学研究センターの田辺秀之准教授は、シンガポール・南洋理工大学が主導する国際的なゲノム研究に参画し、古代のアジア人が人類史上最も長い先史時代の大移動を行い、アメリカ大陸の遺伝的多様性に影響を与えたことを明らかにしました。
この研究は、「GenomeAsia100Kコンソーシアム」*1)の支援を受け、アジア地域の多様な民族グループ139集団、1,537人のゲノムDNA配列データを解析したものです。この研究プロジェクトにはアジア、ヨーロッパ、アメリカの22の研究機関から48名の研究者が参加しています。
今回の研究では、ユーラシアおよび南アメリカの先住民の遺伝情報を詳細に解析し、人類がアフリカから北アジアを経て、南アメリカ最南端ティエラ・デル・フエゴに至る移動経路を明らかにしました。約1万4千年前に南アメリカ北西部に到達した初期移住者は、そこから4つの主要グループに分かれ、それぞれがアマゾンやパタゴニアなどに移住したと推定されました。この長距離移動の過程で遺伝的多様性が減少し、特に免疫関連遺伝子の多様性の低下が、後に持ち込まれた感染症への脆弱性につながった可能性が示唆されました。さらに本研究は、アジア系集団が従来考えられていた以上に高い遺伝的多様性を持つことを明らかにし、ゲノム研究におけるアジア系集団の重要性を改めて強調しました。これらの成果は、人類の進化や環境への遺伝的適応に関する理解を深め、今後の医学や科学の発展に貢献する基盤となることが期待されます。
本研究成果は,2025年5月15日に米国科学誌『Science』に掲載されました。
用語解説
*1) GenomeAsia100Kコンソーシアム
アジア地域に居住する人びとの遺伝的多様性を解明することを目的とした国際的なゲノム研究プロジェクトのこと。2016年に設立され、アジア系の人びとのゲノム情報を収集・解析し、その多様性を明らかにすることを目標としている。
- 詳細は以下のファイルをご覧ください。
リリース文書